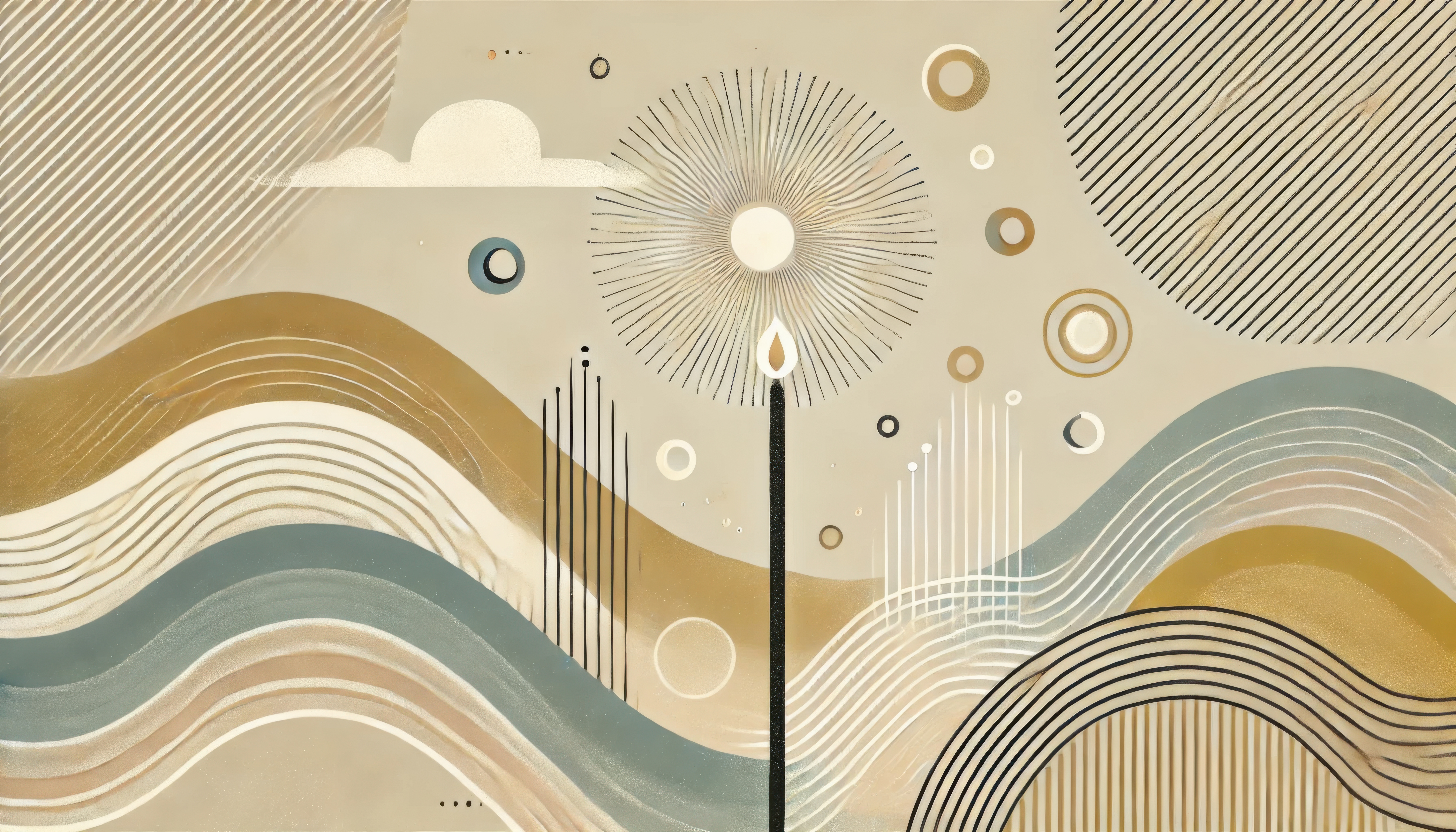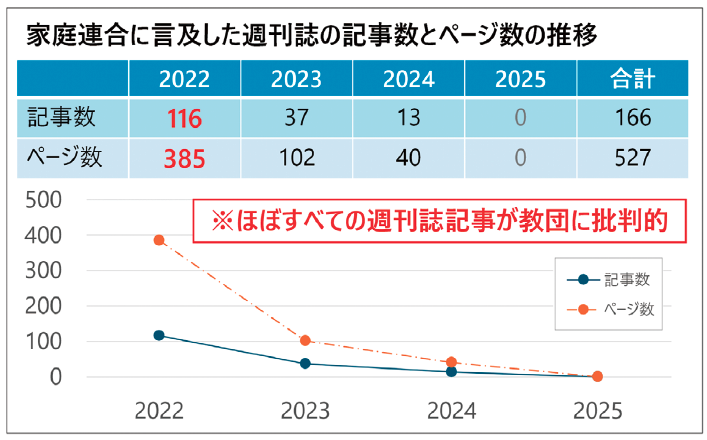出生率低下は「意志」による選択?〜加速する一方の少子化・人口減少〜
出生率低下は「意志」による選択?〜加速する一方の少子化・人口減少〜

今回も出生数回復の兆しは見られなかった。6月4日に厚生労働省が公表した「令和6(2024)年人口動態統計月報年計(概数)」によると、2024年の出生数は前年比4万人余り減少し、68万6061人と70万人を割り込み、合計特殊出生率も1.15と過去最低を更新。人口の自然減も約92万人を記録した。
今後も出産可能年齢の女性が減少し続けるため、劇的な出生数の回復は望めない。したがって人口減を前提とした社会づくりが急務なのだが、それにしても減少スピードが速すぎる。
2017年時点で国立社会保証人口問題研究所は、出生数が70万人を割り込むのは2045年(中位推計)、早くても2031年(低位推計)と見ていた。当時の中位推計から約20年も前倒しされたことになる。
世界的な少子化傾向の要因
先月号の本欄で紹介したニコラス・エバーシュタットの記事によると、出生率の低下は、経済事情など国情が異なる多くの国で進行しており、最も相関関係が深いのが「女性が希望する子供の数」だという。
つまり、経済状況などの客観的指標ではなく、極めて主観的な人間の「意志」が少子化を選択しているというのである。
これに関連する社会変化として、エバーシュタットは「家族形成における革命」、つまり「結婚からの逃避」を挙げる。あらゆる文化伝統において、非婚・晩婚化や一人暮らしが増加しており、「人々はますます自律性、自己実現、そして利便性を重視するようになっている」。そこでは「子供たちは、まさに不便な存在」なのだ。
「幸福」の基準をどこに置くのか?
出生率と「女性の希望」が強く相関しているのなら、女性が「子供を多く持ちたい」と自然に思える社会にならない限り、出生率回復は望めない。
しかしながら、子育てを巡る諸事情を考えると、夫婦共働きの核家族で育てられる子供の数は非常に限られるだろう。大家族を取り戻そうにも、勤務地や住宅の問題、何より「親と一緒に暮らしたい」と望むかどうかという壁が立ちはだかる。
家族に限らず、人と関わることには少なからずストレスがつきものだ。自分自身の欲求や感情を抑制しなければならない場面も多い。現代ではスマホなどの画面越しに、無数の刺激を受け取ることができ、それなりに満足する生活を送ることが可能だ。結婚、家族の必要性は薄れる一方である。
多少の面倒くささがあったとしても、たくさんの家族、子供たちに囲まれて暮らす方が幸せだ…、そんなふうに感じることができる人が増えなければ、子供の数は、今後も減り続ける一方だろう。