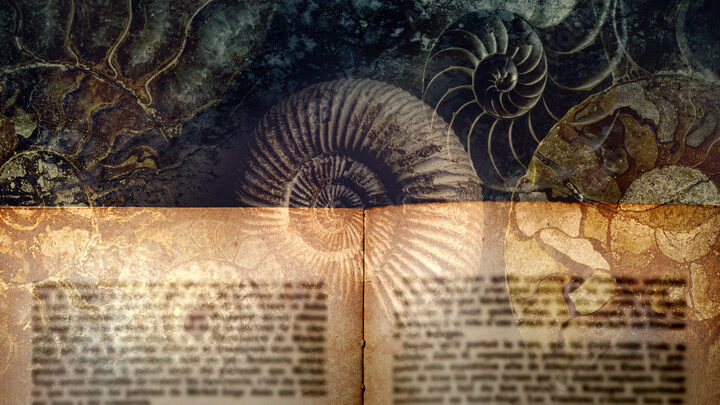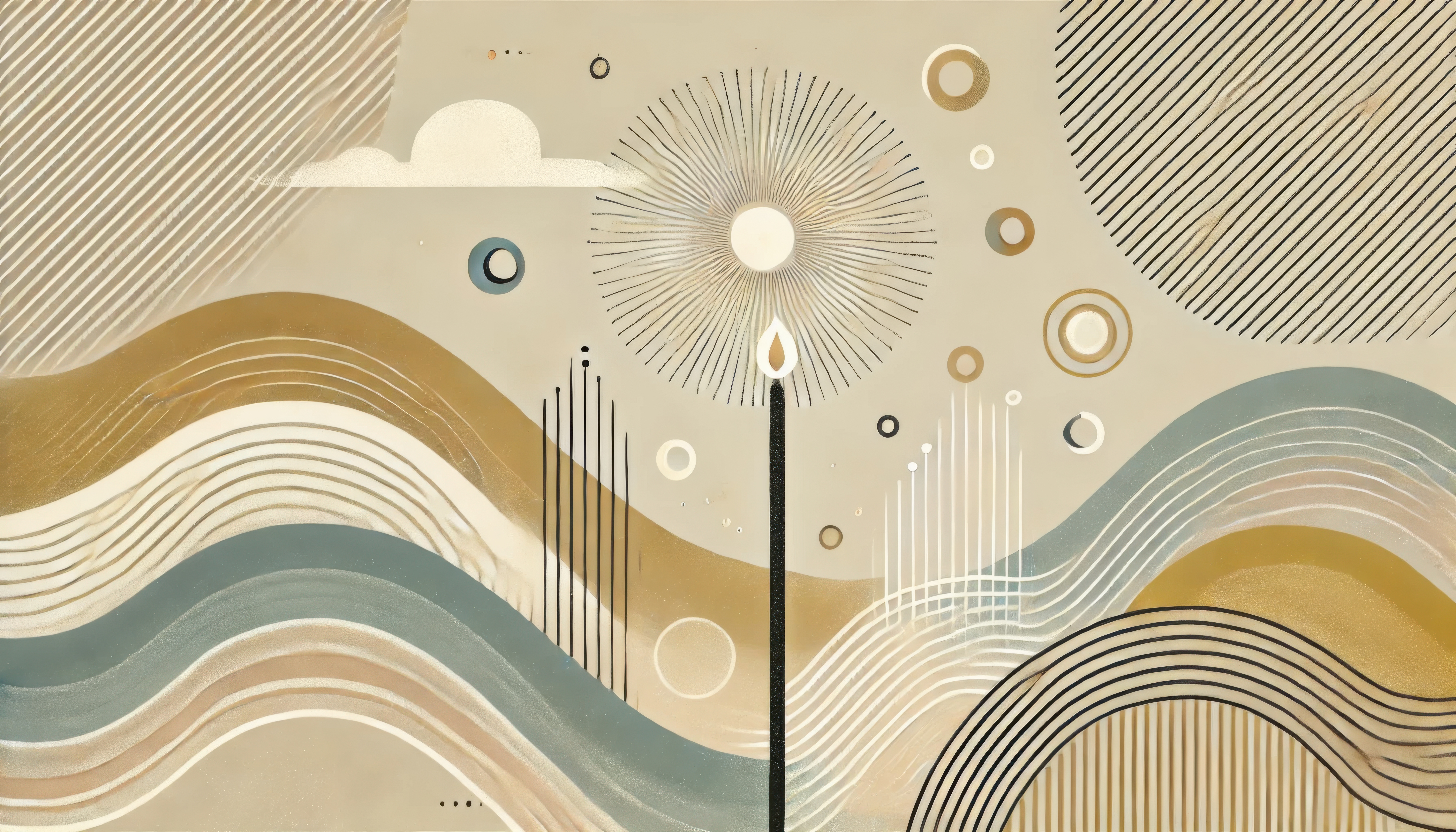戦争と歴史|戦後80年 祖国の歴史と真摯に向き合う年に
戦争と歴史|戦後80年 祖国の歴史と真摯に向き合う年に

「歴史観とは人間の根源である。そして、歴史観とは国家の土台である。国家を国家たらしめるのは、健全な歴史観である」
これはノンフィクション作家の早坂隆氏が、『戦争の昭和史』(2025年5月発行)の「新書版まえがき」に記した言葉である。
2025年2月号の本欄では、今年が昭和100年、戦後80年の節目であることについて言及したが、先の大戦については、「先の大戦を含め、昭和という時代を改めて客観的に確認・検証しようという姿勢を持ち続けたい」と述べるに留めた。
先の大戦、「大東亜戦争」(太平洋戦争)を振り返る上でも、冒頭に紹介した「歴史観」が重要だ。早坂氏は日本で「『祖国の歴史』が蔑ろにされている」ことを嘆きながら、「自虐史観でも自賛史観でもなく、まことの自国史と誠実に向き合う歴史教育を取り戻さなければならない。史実に立ち返らなければならない」と訴えている(同上)。
また「歴史を知ること」の意義については、「国家や社会の今後の行く末を考える上でも、また個人がよりよく生きていくためにも、極めて大切な作業である。歴史の中には多くのかけがえのない教訓が含まれている」と。
今年に入ってから石破茂首相が戦後80年の終戦記念日(8月15日)に、首相談話(80年談話)を出すとの観測が広がり、保守派を中心に反発が起こった。結果的に談話の発出は見送られたが、先の大戦を検証する有識者会議が設置されることに。
その意見聴取などを踏まえ、「歴史観や戦争に対する見解を記者会見などで表明する方向で調整している」という(産経新聞3月28日付)。安倍晋三首相(当時)による「70年談話」の起草に携わった、八木秀治・麗澤大学教授(憲法学)が次のように警鐘を鳴らす。「いかなる形式でも首相が新たに『戦争検証』するのは、対米、対中関係の外交戦略上の観点からも非常にリスクが高い」(同上)。
「歴史の連続性」を見出す
どのような「検証」結果が示されるのか注目したいが、私たち個人においても、先の大戦と向き合うことは必要だ。昨年11月に亡くなった評論家の西尾幹二氏が、1996年、『サンサーラ』という月刊オピニオン誌に「日米を超越した歴史観」と題する評論を寄稿している。今から30年前の文章だが、以下の指摘は全く古びていない。
「いま日本人の心のなかにはふたつの戦争像が棲みついている。終戦まで日本人は自分の戦争を考えていただけで、戦争一般を考えていたわけではない。しかるに50年の歳月とともに、自分の戦争は次第に忘れられ、戦争一般と混同され、他人ごとのように考えられるようになった。たとえばサイパン玉砕の悲劇を単なる歴史の遠い一点景と見なすばかりで、現在の自分の生活にまで一直線につながっている歴史の連続性の課題をそのなかに見届けようとする気持ちは失われてしまった」
西尾氏のいう「戦争像」は「歴史観」とも言い換えられよう。国民の大半が戦後生まれとなった現在、先の大戦を「自分の戦争」と認めることは容易ではない。ただ、先の大戦が「現在の自分の生活にまで一直線につながっている」という、「歴史の連続性」を見出すことはできるはずだ。そのためにも「忠実に立ち返らなければならない」のである。
戦争の過酷な現実を直視する
2018年に「第30回アジア・太平洋賞」特別賞(主催・毎日新聞社)、19年に「新書大賞」(第1位)を受賞した『日本軍兵士ーーアジア・太平洋戦争の現実』(中央公論新社)は、現在までに20万部を突破したベストセラーだ(今年1月には『続・日本軍兵士ーー帝国陸海軍の現実』も出版)。
歴史学者の吉田裕氏(一橋大学名誉教授)による両著は、兵士の目線から「アジア・太平洋戦争における凄惨な戦場の実相、兵士たちが直面した過酷な現実」をよく描き出している。吉田氏が「戦場の凄惨な現実は見すえることを重視」したのは、「1990年前後から日本社会の一部に、およそ非現実的で戦場の現実とかけ離れた戦争観が台頭してきたから」だ。早坂氏のいう「自賛史観」もその一つであろう。自分の見たいものだけ見るという姿勢では、歴史と真摯に向き合うことにはならないのだ。
また、吉田氏は「重要」な発言として、『戦場のコックたち』などを描く、小説家の深緑野分(ふかみどりのわき)氏の発言を紹介する。「戦争を調べていくと、結局、兵士や市民の生活を保てない国が最終的に負けるとわかってきました。戦争を語るとき、戦闘のことが中心で、生活という視点が抜けがちです」(朝日新聞2023年8月16日付)
深緑氏が指摘するように、戦争における国民の「生活」も決して軽視してはならない。もちろん戦場という「死の現場」(金子兜太<とうた>・トラック諸島で従軍した俳人)も見過ごすことはできない。
私たちは先の大戦について、あまりにも無知だ。「歴史の連続性」を取り戻し、「健全な歴史観」を培っていくためにも、さらに史実を学び深める節目の年にしたい。