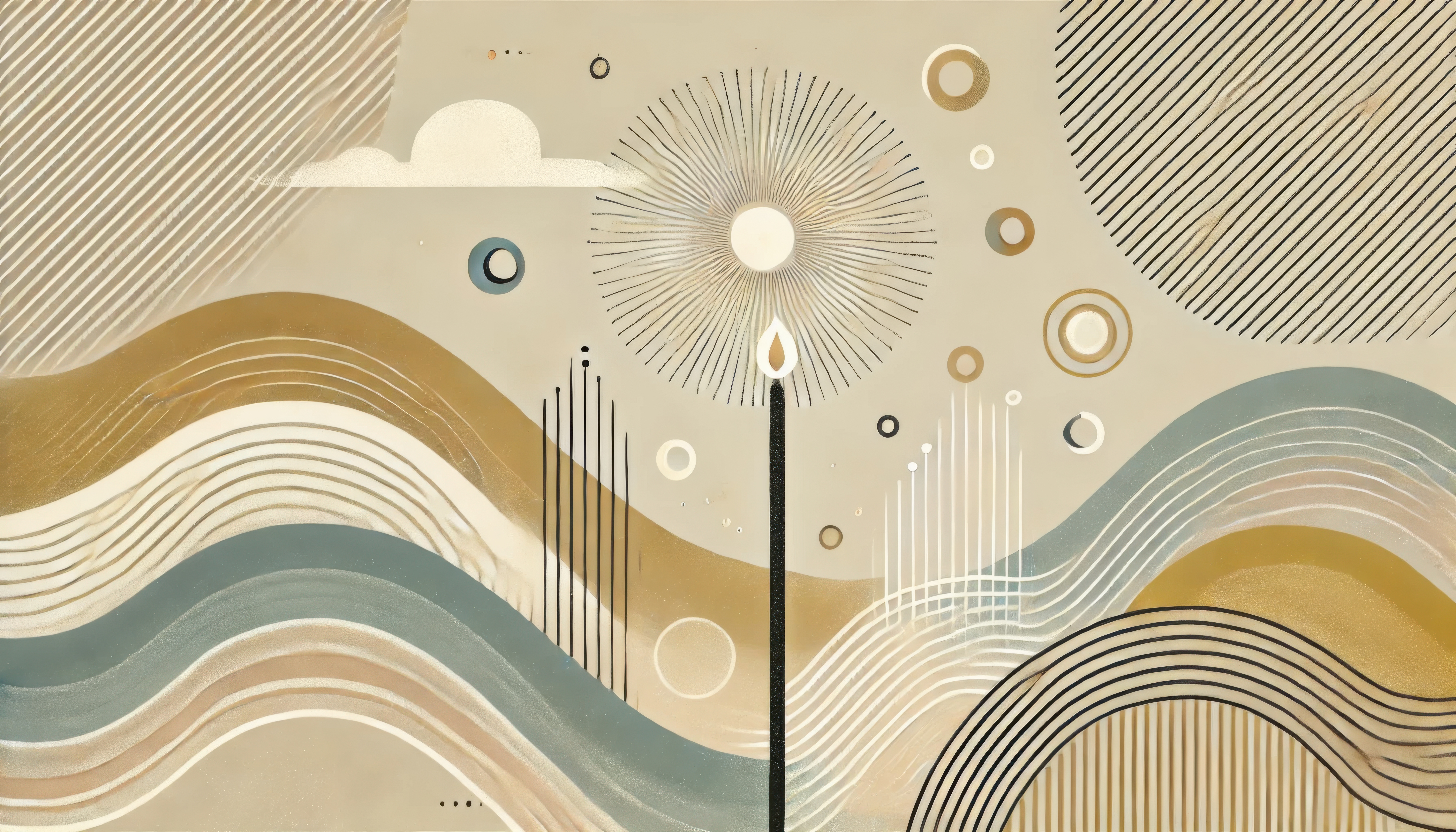「共産主義問題」(後編) | 「憎悪」に囚われない「感情」を
「共産主義問題」(後編) | 「憎悪」に囚われない「感情」を

「共産主義問題」(前編) | 現在も広く浸透する共産主義https://heiwataishi.online/archives/8370
前回、『アメリカを蝕む共産主義の正体』(マーク・R・レヴィン)などを紹介しながら、現在も米国や韓国、日本などに深く根を張る「共産主義問題」について確認した。
ここで言及する「共産主義」は、19世紀後半にカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって体系化された、哲学、歴史観、経済学を含む総合的な社会改革の理論をいう。その中核には、「共産主義唯物論」「唯物弁証法」「唯物史観」などがある。
現在、それらの理論を真剣に学ぼうとする人間は少なくなった。しかし、その影響力が衰え、脅威が薄れたかと言えば、決してそうではない。
共産主義を理論的・知的に学んでいなくても、我知らず共産主義的な考え方に共鳴し、その思想様式に囚われてしまうことが大いにあり得る。そうした囚われに陥らないためにも共産主義の本質を理解することが重要だ。
共産主義は「憎悪の哲学」
UPF共同創設者である韓鶴子総裁は、自叙伝の中で、共産主義を「神様を否定する無神論」「葛藤、闘争、憎悪の哲学」と指摘した。共産主義の本質は「(戦闘的)無神論」「唯物論」であり、「憎悪の哲学」である。ここでは特に「憎悪の哲学」の側面に焦点を当ててみたい。
共産主義を克服する理論体系である「勝共理論」をまとめた、李相軒・統一思想研究院院長(故人)は、共産主義が「今日まで多くの人々」を引きつけてきた理由を次のように解説した。「共産主義は、今日まで多くの人々、特に正義心の強い知性人たちを引きつけてきた。それは、彼らが共産主義のもつ悪魔的要素に気づかないまま、理想世界を約束するその理論に引かれたからであった」(李相軒『頭翼思想時代の到来』)
確かに、昔も今も、共産主義者は高邁な「理想」を掲げ社会変革を追求してきた。では李院長が指摘する「共産主義のもつ悪魔的要素」とは何だろうか。ロシアの著名な宗教思想家のベルジャーエフは、「マルクス主義の悪魔的要素」として、「否定的情熱、憎悪、そして暴力」を挙げている。
ここで想起されるのが、マルクスが19歳の時に書いた詩、「絶望者の祈り」である。その冒頭は以下のようなものだ。
神が俺に、運命の呪いと/軛(くびき)だけを残して/何から何まで取上げて/神の世界はみんな、みんな、なくなっても/まだ一つだけ残っている、それは復讐だ!/俺は自分自身に向かって堂々と復讐したい。/高いところに君臨している/あの者に復讐したい
ベルジャーエフが指摘したとおり、神への復讐心という「否定的情熱、憎悪」が、マルクスの共産主義の原点であり原動力なのである。
ラテンアメリカで活動した著名な革命家チェ・ゲバラは、「憎悪」についてこう述べている。「憎悪は闘争の元素である。敵への無慈悲な憎悪は、我々を、人間の自然の限界の向こう側へと駆り立て、効果的で、暴力的で、そして選り好みする冷酷な殺人機械へと作り変える」
現代の共産主義者や左翼が、ゲバラのように、「冷酷な殺人」をあからさまに叫ぶことはない。しかし、「憎悪は闘争の元素」という表現は、現代の様々な「社会改革」運動を理解する上でも重要なキーワードだ。
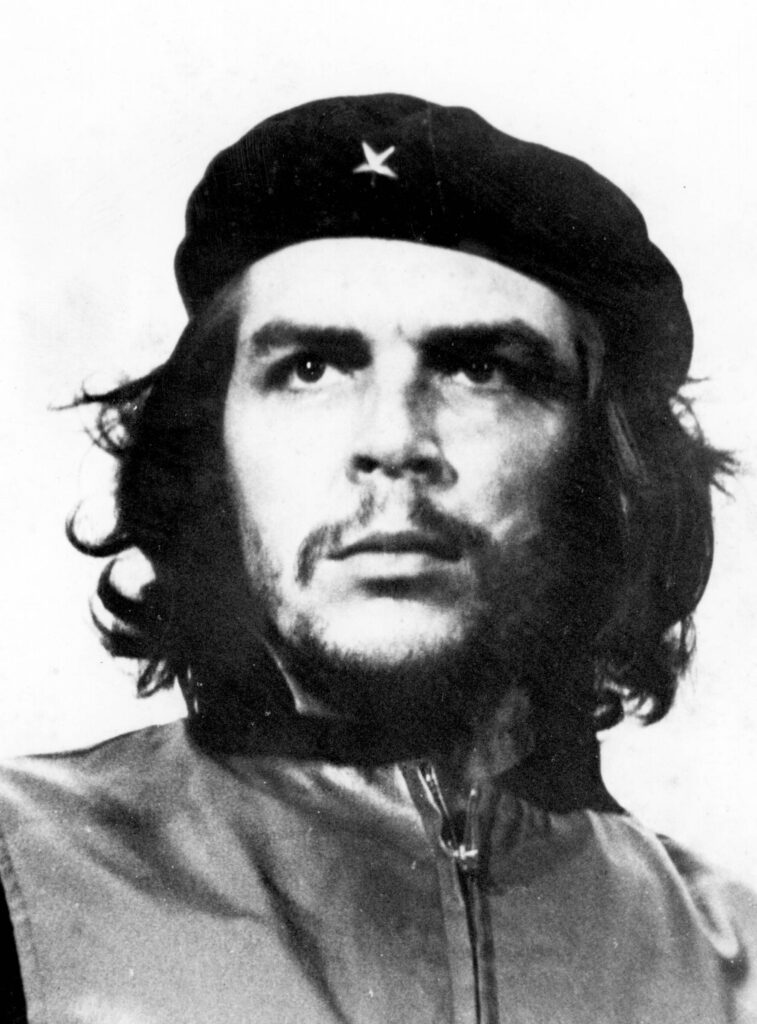
「感情が思考をガイドする」
ここで人間の「感情」と「思考」の関係について考えよう。米国の神経科学者で、「世界で最も引用される科学者の一人」とも言われるアントニオ・ダマシオ氏は、「感情が思考をガイドする」と明言する。同氏によれば「思考形成の中核を占めるのは感情であって、知性ではない」。
「感情が思考をガイドする」という事実に、思い当たる節はないだろうか。どんなに知性を備えた、理性的な人間であろうと、自らの内に「憎悪」のような否定的感情が渦巻いていれば、その否定的な「感情が思考をガイドする」ようになってしまう。したがって一般人もさることながら、為政者など国家における指導層の「感情」が健全なものかどうか、「憎悪」に満ちた人格でないかなどが、重要な判断基準となり得るのだ。人間は「感情の生き物」と呼ばれ、「政治は、感情で動く」とも言われる。政治を含む人間の営為の原動力として「感情」は決して軽視できないのである。
人間が自らの内に「否定的情熱」や「憎悪」を燃え上がらせていれば、対立や闘争、分断をもたらす共産主義的な思考にガイドされ、暴力的な社会変革運動にもコミットしやすくなってしまうだろう。
韓総裁と共にUPFを創設した故・文鮮明総裁は、「葛藤と憎悪の鎖を何によって断ち切るのでしょうか。憎悪に対するより一層大きな憎悪は、かえって恐ろしい憎悪と破壊を呼び起こすだけです。これは、平和に向かう道とはなり得ません」と訴えた。そして、「葛藤と憎悪」を超える方法として、敵対する者さえも愛する、「真の愛」の実践を一貫して提唱した。
社会が右と左、保守とリベラルで分断を深める現代にあって、「憎悪(の哲学)」を超える「感情」が問われている。日本の愛国者よ、国と人々を愛する心で、団結せよ!
世界思想2023年12月号「今月の1テーマ」より